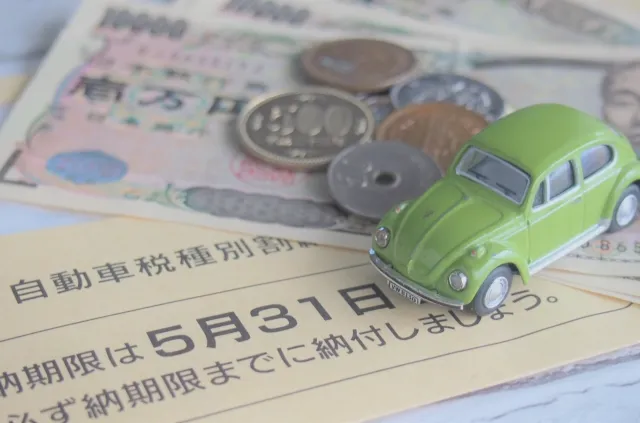
車を購入する際は、本体の購入費用だけでなく、維持費にどれだけお金がかかるかを考慮しなければなりません。ガソリン代や駐車場代のほか、保険料や税金など、車の維持にはそれなりにお金がかかります。特に車の税金に関しては、購入する前にしっかり理解し、どのような出費が生じるのか把握するのが大切です。
この記事では、車の税金の種類や、自動車税の支払い期限などについて紹介していきます。
「車の税金はいつ支払えば良い?」
「どのような税金があってそれぞれの納税期限はいつ?」
車の購入を考えていて、上記のような疑問のある人はぜひチェックしてみてください。
車の税金の種類
まずは車の購入時や、維持していく上でかかる税金について紹介します。車にかかる主な税金は以下の通りです。
- 消費税
- ガソリン税 / 軽油引取税
- 自動車税種別割 / 軽自動車税種別割
- 自動車税環境性能割
- 自動車重量税
消費税はガソリンや軽油を補給する際や、車の購入の際に、本体価格にかかる税金で購入時に支払います。ガソリン税や軽油引取税は、ガソリンや軽油の価格に含まれているので特筆するような問題はないでしょう。
自動車税や軽自動車税の種別割、自動車税環境性能割や自動車重量税についてそれぞれ解説していきます。
税額やいつ支払うかなどについて説明するので、自家用車の購入を考えている人や、税金の名称になじみがないという人は参考にしてください。
自動車税種別割
納税義務のある車の所有者および使用者は、車両を管轄する都道府県に、納期限までに自動車税種別割を納めなければなりません。
自動車税種別割は、4月1日時点で、自動車の所有者(割賦販売などで売主が所有者の場合は使用者)に登録されている人に課せられる地方税です。
税額は、自動車の用途ごとに、総排気量や最大積載量などに応じて定められています。自家用乗用車であれば、年額は以下の通りです。
| 総排気量 | 2019年10月1以降初回新規登録 | 2019年9月30日以前初回新規登録 |
| 電気自動車 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1.0ℓ以下 | 25,000円 | 29,500円 |
| 〜1.5ℓ以下 | 30,500円 | 34,500円 |
| 〜2.0ℓ以下 | 36,000円 | 39,500円 |
| 〜2.5ℓ以下 | 43,500円 | 45,000円 |
| 〜3.0ℓ以下 | 50,000円 | 51,000円 |
| 〜3.5ℓ以下 | 57,000円 | 58,000円 |
| 〜4.0ℓ以下 | 65,500円 | 66,500円 |
| 〜4.5ℓ以下 | 75,500円 | 76,500円 |
| 〜6.0ℓ以下 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6.0ℓ超 | 110,000円 | 111,000円 |
(参考元 : 東京都主税局「自動車税種別割」)
2019年度の税制改正により、新制度が適用された10月以降とそれ以前の購入とで、納める税額が異なります。改正により税額は軽減されましたが、2019年9月以前に登録された車両は改正前の税額になるので、中古車を検討されている方は注意しましょう。
軽自動車税種別割
軽自動車税種別割は、自動車税種別割と同様に、4月1日時点での所有者(所有者がローン会社などの場合は使用者)が納めます。軽自動車税は市区町村が管轄しており、軽自動車の納税義務者は、住所地の市区町村に対して納税しなければなりません。
税額は車種区分と用途によって設定されています。普通自動車との比較として、4輪以上の乗用車の年額を紹介するので参考にしてください。
| 標準旧税率 | 標準新税率 | 経年車重課税率 | |
| 自家用乗用車 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用乗用車 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
(参考元 : 総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」)
2016年度に新しい制度が適用され、最初の新規検査を2015年の4月1日以降(新税率)に受けた軽四輪車と、2015年3月31日まで(旧税率)に受けた軽四輪車で納税額が異なります。
さらに最初の新規検査から13年を経過している軽自動車は、環境負荷の低減を進める施策から、重課が適用される(経年車重課)ので、中古車購入の際は注意しましょう。
自動車税環境性能割
自動車税環境性能割は、普通自動車であれば都道府県、軽自動車であれば市区町村の管轄となり、車の取得時に納付します。税制改正で廃止された「自動車取得税」に代わるもので、2019年の10月に導入された自動車の取得時に課せられる地方税です。
税額は「自動車の通常の取得価額×税率」で算出します。新車や中古車に関わらず、燃費性能が優れているほど、税率が下がるシステムです。
自家用の普通自動車であれば、税率は0〜3%、営業用の車や軽自動車であれば、税率は0〜2%になります。登録時に支払う税金なので、購入時の費用をおさえたい人は税率をチェックしておくようにしましょう。
自動車重量税
自動車重量税は、乗用車の車両の重量に応じて課せられ、新規登録時に3年分、車検時に2年分をまとめて支払う国税です。
自家用の普通自動車なら、年額は以下の表のように、0.5tごとに加算されていきます。
| 車両重量 | 自動車重量税(年額) |
| 0.5t以下 | 41,00円 |
| 〜1.0t以下 | 8,200円 |
| 〜1.5t以下 | 12,300円 |
| 〜2.0t以下 | 16,400円 |
| 〜2.5t以下 | 20,500円 |
| 〜3.0t以下 | 24,600円 |
(参考元 : 令和3年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方 その2)
重量税は軽自動車も対象ですが、新規検査から13年未満の自家用軽自動車(エコカーを除く)であれば、重量に関わらず年額は3,300円です。新規登録時であれば、3年分の9,900円、検査時は2年分の6,600円を納めます。
燃費基準を満たしているエコカーであれば、重量税の免税や減税を受けることも可能です。一方でエコカー以外の自動車は、新規登録からの経過年数で自動車税重量税の重課があるので、中古車の購入時は注意しなければなりません。
0.5t以下の自家用の普通自動車の場合、13年経過だと年額が5,700円(自家用の軽自動車は4,100円)、18年経過であれば年額は6,300円(自家用の軽自動車は4,400円)です。
自動車税種別割はいつどのように支払う
自動車税種別割について、いつ支払うのか、またどのように支払えば良いのか解説していきます。
自動車税種別割は年ごとの税金で、送付される納税通知書に従って定められた期限内に支払わなければなりません。
送付時期や納期期限は、基本的に地域で決まっているので、余裕をもって準備しておくのが大切です。納期限や支払い方法について詳しく解説していくので、車の購入を検討している人や、納期限がいつ頃なのか知りたい人は参考にしてください。
送付される納税通知書を使用して支払う
一般的には毎年5月上旬頃に、自動車税種別割の納税通知書が送付されます。管轄の都道府県の税事務所から送られてきますが、1部の地域では、送付時期が異なる場合もあるので注意しましょう。
通常、送付先は4月1日時点で車検証に記載されている車の所有者の住所です。ただ、ローンで車を購入している場合、ローン会社が所有者になっているケースもあります。
その場合、納税義務者は所有者ではなく使用者です。車検証の使用者欄に記載されている住所に納税通知書が届きます。
納税義務のある所有者か使用者に届くようになっているので、納税通知書が届いたら期限を過ぎないように支払いを行いましょう。
自動車税種別割の納付期間
自動車税種別割は、一般的に5月から納付が可能です。ほとんどの地域では、納税通知書は5月初旬に発送されます。
5月上旬に通知書が届く場合、納付期限は基本的に5月31日です。
ただし、1部の地域では、納税通知書の発送が6月上旬のケースもあります。
この場合は納付期限も6月30日になっているので、期限までに支払えば問題ありません。
5月でも6月でも、支払期日となる末日が土日の場合は、期日が翌月曜日まで期日が延びるのが一般的です。
購入した時は月割りで登録時に支払う
自動車税種別割は、4月1日時点での所有者に対しての1年度分の課税ですが、4月2日以降に購入すればその年度の納税が不要というわけではありません。
普通自動車を4月2日以降に購入した場合、新規登録の翌月からその年度末まで、月割分の自動車税種別割が課せられます。
自動車を購入して運輸支局で登録する際、車検証の交付を受けた後に、隣接する自動車税申告窓口で納税しなければなりません。ただし、3月に新規登録する場合は、購入時の自動車税の支払いは不要です。
3月以外は、購入時に月割課税の支払いがあるということを、覚えておきましょう。
自動車税種別割の納付先と納付方法
自動車税種別割は、金融機関やコンビニで支払えるほか、各都道府県の税事務所の窓口で納付できます。地方税なので、納付先は各都道府県の税事務所です。
利用できる支払い方法や、特徴についてまとめたので、参考にしてください。
| 支払い方法 | 特徴 |
| 納付書で現金払い | ・税事務所の窓口 / 指定の金融機関 / コンビニで支払い可能
・その場で領収書を受け取れる |
| クレジットカード | ・パソコンやスマホを利用しての支払い
・税額に応じて決済手数料が発生 ・領収書の発行に時間がかかる |
| 口座振替 | ・事前に申し込みをすれば支払い期限日に引き落とし |
| Pay-easy/PayB | ・ペイジーかペイビーマークのついている納付書であれば指定金融機関のATMやアプリで納付可能
・インターネットバンキングやモバイルバンキングは事前申し込みが必要 |
| スマホ決済アプリ
(PayPay・LINE Pay・au Payなど) |
・手数料無料
・支払いによってポイントが付加される |
| 電子マネー | ・セブンイレブンやミニストップなど1部のコンビニのみで対応 |
クレジットカード決済やインターネットバンキングで納付した場合、領収書が発行されず、納税証明書の発行が2週間後以降になってしまいます。
納付期間から車検まで期間がなく、領収書や納税証明書が急ぎで必要な場合は、金融機関やコンビニ、税事務所で支払うのが確実です。
自動車税種別割の納税通知書が手元にない場合の対処法
納税通知書が手元になくて納付ができない場合や、納付期限を過ぎてしまった場合の対処法について解説します。自動車税は納付期限までに納めないと、延滞金が発生し、最悪の場合差し押さえになる場合もあるので注意が必要です。
以下のようなケースになっても、放置しないようにしましょう。
・自動車税納税通知書をなくしてしまった場合
・自動車税納税通知書が届かない場合
・納付期限が過ぎてしまった場合
各ケースについて、対処法を具体的に解説していくので、参考にしてください。
自動車税納税通知書をなくしてしまった場合
納税通知書をうっかりなくしてしまった場合は、すみやかに管轄の税事務所に連絡して、再発行をしてもらいましょう。
なくしてしまったからといって、支払わずに放置しておくと、催促状は届きますが、納付期限を過ぎた時点から延滞金も発生してしまいます。
車検証に記載されている住所地の都道府県の税事務所で、納税通知書の再発行の依頼が可能です。
東京都であれば、「東京自動車税コールセンター」が設置されており、電話で再発行をお願いすれば、再度納税通知書を郵送してくれます。
自動車税納税通知書が届かない場合
車を所有、もしくは使用しているのに納税通知書が届かないという場合は、管轄の税事務所や自動車税コールセンターに確認の連絡をしてみましょう。
自動車税納税通知書が届かない場合は、以下のような原因が考えられます。
・引越しをして車検証の住所変更をしていない
・車検切れをしている
納税通知書は車検証に記載されている納税義務者の住所に届くので、車検証の住所変更手続きを行なっていないと届きません。郵便局に転居届を出していれば、1年間は新住所に転送されますが、転送期間が終了していると受け取れなくなってしまいます。
車検切れの車に関しては、1部の都道府県は車検が切れて4月1日をむかえた車について、自動車税の課税を保留する場合があり、納税通知書が送付されません。
自動車税の課税保留は、都道府県によって適用が異なるので、管轄の税事務所に問い合わせるようにしてください。
いずれにしても、自動車税の納付期間は1ヶ月もないので、車を使っているのに納税通知書が届かない場合は、管轄の税事務所に確認するようにしましょう。
納付期限が過ぎてしまった場合
うっかり納付期限を過ぎてしまった場合は、管轄する自治体によって定められている支払い方法を確認しましょう。納付期限を過ぎた場合の支払い方法は、自治体によって異なります。
期限を過ぎると、支払い方法や納付場所が制限され、ペイジーでの支払いやクレジットカード払いができなくなるケースが多いです。
納付書にコンビニ取扱期限が記載されている場合は、その期限までであればコンビニで支払いができます。また、自治体によっては、期限が過ぎていても指定金融機関で納付書での支払いが可能です。
自治体によってさまざまなので、自動車税納税通知書の記載事項を確認するか、管轄の税事務所に問い合わせてみてください。
軽自動車税種別割の納期限や支払う際のポイント
軽自動車税種別割をいつ支払うか、またその支払いをする際の注意点などについて、簡単に紹介していきます。軽自動車税種別割の納税の流れは、普通自動車とおおむね似ていますが、異なるポイントがいくつかあるので注意しなければなりません。
明確な違いとしては、管轄が都道府県でなく市区町村である点です。納税通知書を紛失した場合や、納付期限をすぎた場合などは、基本的には車検証に記載された住所地の市区町村に問い合わせます。
注意が必要なポイントについて解説していくので、軽自動車の取得を検討している人などは、参考にしてください。
軽自動車税種別割はいつ支払う
自動車税同様、軽自動車税種別割も5月末日までの納付が一般的ですが、納期限は事前にしっかり確認しておくのがおすすめです。納付期限は、納税通知書が発送された月の末日に設定される傾向にあり、自治体によっては納期限が4月や6月の末日の場合もあります。
軽自動車税は市区町村の管轄なので、該当する自治体のHPなどをチェックしてみてください。昨今では4月末日であった納期限を、5月末日に変更した自治体も多くあります。
期限内に納付できるよう、管轄の市区町村の納付期限を確認しておくようにしましょう。
4月2日以降の購入であれば月割の納税は不要
普通自動車は取得後、登録の際に月割で自動車税種別割を納税しますが、軽自動車の場合は月割分の納税は不要です。軽自動車税種別割は4月1日を基準日として課税していますが、月割課税制度がありません。
したがって、4月2日に軽自動車を購入しても、同年度の3月に購入しても、課税はどちらも翌年度からになります。
一方で、4月2日に廃車をしてしまっても、前日まで所有していた場合は、その年度は課税対象です。軽自動車を廃車する際は、タイミングに充分気をつけましょう。
軽自動車税種別割を支払う際の注意点
軽自動車税種別割は、自治体によってさまざまな支払い方法で納付できますが、納税証明書をその場で渡してもらえる現金払いが望ましいです。
軽自動車は、車検時に書面で納税証明書を提出しなければなりません。
昨今、自動車税は納税証明書の電子化が進み、納税証明書の提出を省略できる場合がありますが、軽自動車税には導入されていないのが現状です。
クレジットカードやキャッシュレスでの決済もできますが、納税証明書の受け取りに数日〜2ヶ月程度かかる場合もあれば、窓口での申請が必要なケースもあります。
車検まで期間がない場合は、コンビニや指定された金融機関、市区町の納税課で現金で納付して、納税証明書をその場で受け取れるようにしましょう。
納付時期を把握してきちんと納税しよう
年ごとに納付する自動車税や軽自動車税の種別割は、納付期間をしっかり把握して、支払いもれがないようにしましょう。
昨今はエコカー減税や、環境配慮型税制など車の減税制度が充実しているので、未払いによる延滞金などで損をしてしまうのはもったいないです。
自動車税が未払いのままだと、車検を受けられなくなったり、財産を差し押さえられたりする場合もあります。
とはいえ、納税通知書が届かないケースなどは、気づきにくいかもしれません。
納税通知書が例年より遅いと感じたら、管轄の税事務所や自治体の納税課に早めに連絡してください。
自動車重量税も2年ごとの車検時の納税になるため、うっかり準備し忘れてしまう人も多いです。納付期間や車検時期は、なるべく意識するように努め、適切に税を納めましょう。










